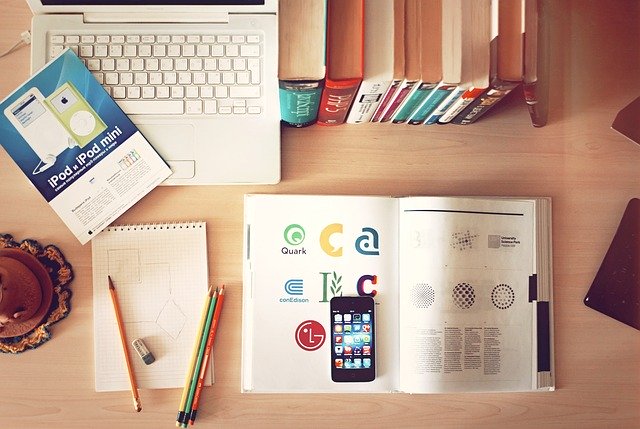
2020年より、小学校においてプログラミング教育が必修化されます。自校の生徒に最適な教材を探している方も多いのではないでしょうか。
今回はまず、小学校のプログラミング教育の事例を2種類紹介していきます。他校の事例を参考にすることで、算数や理科の授業で教材をどう使うか、イメージが湧きやすいかと思います。
次に、プログラミング教育に欠かせない6種類の教材を紹介します。言語型やロボット型など、種類ごとに紹介していることが特徴です。小学校によって合う種類・合わない種類がありますので、ぜひタイプ別に見比べてください。
小学校のプログラミング教育事例【算数&理科】
小学校にプログラミング教育必修化が適用されるのは2020年度です。必修化を念頭に、一部の学校ではすでにプログラミング教材を導入しています。
各校の事例を知っておくことで、自校にどのような教材を導入すればよいか、参考になるはずです。
画像出展:プログラミング教育ポータル(文科省・総務省・経産省)
事例(1)算数(小学5年生)
杉並区立西田小学校では、小学5年生の算数で「正多角形をプログラムを使ってかこう」の授業を行っています。使用する教材は、ビジュアル言語型の「Scratch」です。
この学習は、正多角形の意味を理解したうえで、プログラムを使って正多角形を実際に書く方法を学ぶことが目的です。
具体的な授業内容は次のような手順に沿って行います。
- ワークシートを使って正多角形の内角の大きさを確認する
- 物差しや分度器で紙に正多角形を書いてみる
- 今度はScratch上で正多角形のプログラムを組む
- 組み上げたプログラムで正多角形が書けると完成
正多角形は「辺の長さが全て等しく,角の大きさも全て等しい」ことが特徴です。まずは紙に正多角形を書くことで、正多角形の構造を掴むことができます。最後にプログラミングによって正多角形を完成させることで、プログラムの組み立て方の理解へと繋がります。
事例(2)理科(小学6年生)
三鷹市立北野小学校では、小学6年生の理科で「電気を無駄なく使うにはどうしたらよいかを考えよう」の授業を行っています。使用する教材は「レゴ® WeDo 2.0」です。
プログラミング教育の目的は、スイッチのオン・オフによって電気制御の仕組みを知り、電動アイテムの使い方を知ることです。
具体的な授業内容は次のような手順に沿って行います。
- スイッチロボの仕組みを知る
- プログラミングの仕組みと操作方法を理解する
- 「スイッチを入れる」プログラムを実施
- 「スイッチを切る」プログラムを実施
- 学習の振り返り・学習感想文の作成
ロボットは、プログラムの内容に従って命令の手順ごとに動きます。この授業では実際にロボットの動作を観察しながら、プログラムが物を動かす仕組みを学ぶことができます。
プログラミング教育必修化で利用される教材6選【種類別】
プログラミング教育必修化によって利用が検討される教材について、ここでは3つの種類から紹介していきます。本記事で紹介する教材は、すべて小学生向けです。
画像出典:プログラミング教育ポータル(文科省・総務省・経産省)
1.ビジュアル言語・テキスト言語
プログラミング教材は、主に言語タイプがよく利用されています。
画面上に並んだアイコンを視覚的に操作する「ビジュアル言語型」、文章形式でプログラミング言語を記入していく「テキスト言語型」があり、それぞれ種類は多様です。
Scratch(スクラッチ)
Scratchはビジュアル言語型教材で、マサチューセッツ工科大学のメディアラボが無償公開しています。
画面上に用意されたブロックを組み合わせることで、独自のプログラムを作ることができます。たとえば、「10歩動かす」「1秒待つ」といったプログラムを組んでおくと、画面上のキャラクターが実際に動く仕組みです。
Scratchを利用するメリットは、ビジュアル言語の基本的な機能を無料で利用できることでしょう。
マイクロビット(BBC micro:bit)
マイクロビットは、クレジットカードよりも一回り小さい教育用のコンピュータです。
温度センサーや加速度センサー、無線通信機能などを備えています。段ボールやペットボトル製の工作作品に導入することで、プログラム通りの動きを実演できます。パソコンでプログラムを組み、転送ケーブルによって機器にデータが反映されます。
マイクロビットを利用するメリットは、プログラミング言語を学べるほか、プログラムによって物が動く仕組みを理解できることです。
2.ロボット型学習教材
ロボット型の学習教材は、プログラムと連動した機器や工作機械などを利用します。コンピュータでプログラムした内容に従って付属の機器が動くため、プログラミングの仕組みが視覚的に理解しやすいといえるでしょう。
エムブロック(mBlock)/エムボット(mBot)
エムブロックは、付属のロボットキット「エムボット」を動かすプログラムが構築できる教材です。
ロボットには複数のセンサーに加え、ブロック、タイヤなどがセットになっており、機械の構造的な仕組みを学ぶことができます。プログラムを組むときはビジュアル言語ソフトを使用するため、小学生にも操作しやすい点が特徴です。
レゴ・マインドストームEV3
レゴ・マインドストームEV3は、レゴブロックを使ったプログラミング教材です。
まずは、レゴブロックを自分なりに組み立て、オリジナルの教育ロボットを作ります。その後、付属するプログラミングソフトで動作構造を指示すると、その内容に沿ってロボットが動く仕組みです。
小学生にも扱いやすいく、馴染みの深いレゴブロックを使うため、プログラミング教材としても活用しやすいメリットがあります。
3.ゲーム系学習教材
プログラミング教育必修化に向け、ゲームと教育を組み合わせた教材も出てきています。数ある教材のなかでも、小学生にとってもっとも馴染みやすいといえるでしょう。
教育版マインクラフト
マインクラフトは、ブロックで出来た世界のなかで、一つひとつのブロックを組み合わせて建物や家具など独自の世界を作り出せるゲームです。なかでも、プログラミング教育用に特化したものが「教育版マインクラフト」です。
もともとマインクラフトは、キーボードやゲームパッドなどでキャラクターを操作します。一方、教育版マインクラフトでは、あらかじめゲーム内でプログラムを組むことができ、その内容に従ってキャラクターを自由に動かすことができます。
ゲーム内では、クラスメートと共同して世界を作っていくことになります。そのため、プログラムについて学べるだけではなく、他者との協調性まで身に付けられることが大きなメリットです。
ルーピマル(LOOPIMAL)
ルーピマルは、プログラミングと音楽を組み合わせた教材です。
画面下部にあるブロックを自由に並べ替えると、自分なりのメロディやリズムを作り出せます。画面上では、作成した音楽に合わせて動物が踊りだすので、小学生向けの教材として最適です。
【まとめ】プログラミング教育の目的に沿った教材を選ぶ
プログラミング教育必修化に向けてさまざまな教材が発表されており、今後はますます種類が増えていくことでしょう。
今回は、小学生向けのプログラミング教材として、計6種類を紹介しました。教育の目的や内容に合わせて、自校に最適な教材をご選択ください。


